本ブログでは最初に始める投資として、インデックス投資をおすすめしています。
インデックス投資はドルコスト平均法でコツコツと積み立てることで、長期的な資産拡大に向いている投資法です。
インデックス投資については、以下の記事で紹介しています。
インデックス投資とは?長期保有することで資産の最大化を狙う投資法
さて、ここで1つ疑問があります。

インデックス投資で積み立てた資産はどのように売却すれば良いのかな?
本記事ではこの疑問の回答として、インデックス投資の出口戦略として有名な4%ルールによる取り崩しについて解説していきます。
これから資産を形成していく方も、今後売却していこうと考えている方も、ぜひ参考にしてみてください。
4%ルールとは?
4%ルールとは、1998年にトリニティ大学の3名の教授によって発表された通称「トリニティスタディ」という論文にある有名なシミュレーションです。
その内容としては
- 1926年から1995年の70年を対象期間として
- 株式50%、債券50%のポートフォリオで
- 貯めた資産から年4%を取り崩す
というシミュレーションになります。
この状態で30年経過しても95%の確率で資産が残っているという結果になったということで有名になりました。
具体的な金額で例をあげると、3000万円投資していて4%にあたる120万円ずつを毎年取り崩しても30年後に95%の確率で資産が残っているということになります。
実際の表を見てみてください。

黄色の部分が95%になっており、これが4%ルールとして世の中に広がりました。
トリニティスタディでは株式50%、債券50%以外にも
- 株式100%
- 株式75%、債券25%
- 株式25%、債券75%
- 債券100%
といったシミュレーション存在しています。
以下に載せましたので、ぜひ参考にしてみてください。




またトリニティスタディでもうひとつ有名なのが、株式75%、債券25%のポートフォリオで同じように4%ずつ取り崩していった場合、30年後に残っている資産の中央値が当初資産の8倍という結果もあります。
先ほどの3000万円を例にあげると、30年後には2億4000万円となっている計算なので驚きの結果ですよね。
資産運用の世界では「年間生活費の25倍を投資に回して、そこから4%ずつ取り崩して生活しても資産が減らない」と言われていますが、これは4%ルールが元ネタになっています。
ちなみに1926年~1995年という期間ですが
- 1929年・・・世界恐慌
- 1939年・・・第二次世界大戦
- 1973年・・・第一次オイルショック
- 1979年・・・第二次オイルショック
- 1987年・・・ブラックマンデー
といった歴史上の事件が多く含まれており、暴落も想定されています。
トリニティスタディに用いられた株式・債券はそれぞれ
- 米国株インデックス(S&P500)
- 米国債券(長期高格付社債)
になります。
4%ルールを長持ちさせる方法
ここまで4%ルールについて解説してきましたが、以下のような問題点があります。
- 5%の確率で失敗する
- 実際には税金や手数料がかかるため、4%で取り崩したとしても手取りは少なくなる
- アメリカの研究なので、為替リスクが存在する日本の場合は参考程度となる
2.、3.についてはどうしようもないため、1.を回避する方法について解説していきます。
暴落時に備えてあらかじめ現金を用意しておく
4%ルールを長持ちさせるために、暴落時に備えてあらかじめ現金を用意しておく方法です。
以下の図は、1980年1月から2019年6月までの世界の株価の推移になります。

20%以上の暴落が起きたのは8回で、その期間も2ヶ月~30ヶ月となっています。
上記のデータを参考にすると、最大3年分の生活費を現金で持っていれば、暴落時に4%ルールの取り崩しは行わないことで長持ちさせることができます。
暴落時は取り崩す率(%)を減らす
暴落時に備えて現金を持っておくのではなく、取り崩し率(%)を減らすという手もあります。
暴落時は4%ルールではなく3%ルールに変更して取り崩すということです。
取り崩し率が下がってしまうので、その分生活が苦しくなってしまうという欠点があります。
しかし過去のデータを見る限り、下落相場よりも上昇相場の方が期間も長いですし、4%ルールを長持ちさせるという点において、このような調整も必要になってくると思います。
4%を定率で取り崩す
最後に4%ルールを定率で取り崩すことについて解説していきます。
トリニティスタディでは定額で取り崩しています。
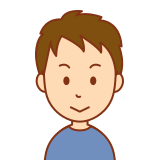
定額?定率?何それ?
となっているかもしれませんので、引退時の資産が3000万円だったと仮定して解説します。
定額取り崩しは3000万円の4%である120万円という固定の金額を毎年取り崩すということ。
定率取り崩しは今持っている資産の4%を毎年取り崩すということ。
- 3000万円の場合、4%である120万円
- 2000万円の場合、4%である80万円
- 4000万円の場合、4%である160万円
毎年持っている資産によって金額が変わってきます。
定率で取り崩すことで理論上資産がなくなることはありません。
デメリットとしては、株式相場によって取り崩し金額が変わってくるため、生活費の確保という点では安定していません。
しかし、4%ルールを長持ちさせる方法のひとつとして知っておくのもありだと思いますので、必要にお応じて検討するのが良いでしょう。
ちなみに、4%ルールを定率で取り崩す方法は名著「ウォール街のランダムウォーカー」で紹介されていますのでぜひ読んでみてください。
まとめ:4%ルールを理解して資産運用に役立てよう!
本記事では資産運用(特にインデックス投資)の出口戦略として4%ルールについて解説してきました。
- アメリカのトリニティ大学の教授3名が発表した通称「トリニティスタディ」の論文にあるシミュレーション
- 株式50%、債券50%を定額で毎年4%ずつ取り崩すと30年後に95%の確率で資産が残っている
また4%ルールを長持ちさせる方法として
- 暴落時に備えてあらかじめ現金を用意しておく
- 暴落時は取り崩す率(%)を減らす
- 4%を定率で取り崩す
ということについても紹介してきました。
資産形成期の方はまだ先の話になりますが、出口戦略についても意識することでモチベーション維持にもつながるかと思います。
今回解説した4%ルールによる定額取り崩し・定率取り崩しについてですが、楽天証券では「定期売却サービス」というものがあります。
定期売却サービスでは
- 金額指定
- 定率指定
- 期間指定
という3種類あり、このうち1.が定額取り崩し、2.が定率取り崩しになりますね。
ライバルのSBI証券では記事執筆時点で「1.金額指定」しかできませんので、選択肢の幅が多い楽天証券がおすすめです。
楽天ポイントを絡めた投資も可能なので、持っていて損はない証券会社ですので口座開設されていない方はぜひしてみてください!

関連記事です。
楽天証券をおすすめする理由について記事を書いていますので、こちらもぜひ読んでみてください。
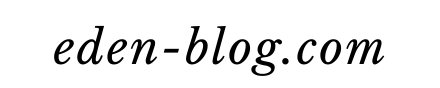

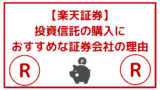


コメント