皆さんはiDeCo(イデコ)についてご存知でしょうか?
2001年10月に制度が始まって以降、一部の人しか加入できなかったのですが、近年は加入条件が緩和されてきており、特に2022年10月からの条件緩和によってほぼ誰でも利用できる制度になります。
iDeCoに加入することによって税制優遇のメリットが受けられる一方、デメリットも存在します。
そこで、本記事では
- iDeCoの概要
- iDeCoのメリット
- iDeCoのデメリット
について解説していきます。
iDeCoの概要
iDeCoとは個人型確定拠出年金の愛称のことで、自分自身で老後資金を作るための制度で、国民年金被保険者である20歳~64歳までの人が加入できます。(2022年5月から)
老後のお金について考えたときに、一番始めに思い浮かぶのが年金ですよね。
日本の年金制度は家に例えられることが多いですが、主に
- 国民年金(1階部分)
- 厚生年金(2階部分)
の2つがあります。
iDeCoはここに3階部分として加わります。
現在、国民年金・厚生年金の平均受給金額は以下の通りです。
- 国民年金…約5.6万円/月
- 厚生年金…約14.6万円/月(国民年金含む)
この金額を見てどう感じるでしょうか?
「十分だよ!」という人もいるかもしれませんが、多くの人はこれだけだと老後資金としては心もとないのと感じるのではないでしょうか。
そういった方向けにiDeCoを追加することで、老後資金を上積みする狙いがあります。
では一体どれだけ貰えるのかですが、iDeCoでは自分自身で掛け金を拠出・商品を選択し運用する方式のため運用成績によって変わってしまいます。
そのため国民年金・厚生年金のように、一概に「これだけの金額貰えますよ」とは言えない状態です。
また職業によって掛け金の限度額が異なります。
iDeCo公式サイトに図があったので引用します。

上記の金額を必ず拠出ししないといけない訳ではなく、掛け金の最低金額は5,000円で1,000円単位で変更することができます。
ここまでiDeCoの概要を説明しましたが、次にiDeCoのメリット・デメリットを見ていきましょう。
iDeCoのメリット
iDeCoのメリットは以下の通りです。
- 掛け金が全額所得控除になる
- 運用益が非課税になる
- 受け取り時に税制優遇がある
- 差し押さえ禁止財産となる
それぞれ見ていきましょう。
iDeCoのメリット①:掛け金が全額所得控除になる
iDeCoは自分自身で掛け金を拠出して運用しますが、その掛け金が全額所得控除となり所得税・住民税を安くすることができます。
どれくらい安くなるのかについて、みずほ銀行に例があったので紹介します。
例:45歳 会社員 年収600万円 毎月1.2万円拠出(年間合計14.4万円)
| iDeCoに加入しない場合 | iDeCoに加入した場合 | 備考 | |
| 課税所得 | 298万円 | 283.6万円 | iDeCoにより4.4万円控除 |
| 税額 | 59.6万円 | 56.72万円 | 28,800円減税 |
この例では毎年28,800円の節税になります。
45歳なので60歳までこのままと仮定すると、15年間で合計43.2万円の節税になります。
人によって節税額は異なりますが、単純にメリットを活かすのであれば
- 年収を高くする
- 若いうちから始める
- 掛け金上限まで拠出する
ということになります。
iDeCoのメリット②:運用益が非課税になる
メリット①でiDeCoの掛け金が全額所得控除になると解説しましたが、運用した利益についても非課税になります。
通常、運用した利益に対して約20%(20.315%)の税金がかかりますが、iDeCoの場合は非課税となります。
例として、メリット①で紹介した45歳会社員の人で見ていきましょう。
条件:毎月1.2万円を15年間拠出 利回りを5%
とした場合、楽天証券の積立かんたんシミュレーションでシミュレーションした結果は以下の通りです。

元本216万円、運用益104万7,467円で合計320万7467円になりました。
本来だと運用益の104万7,467円に対して約20%の税金がかかるため、約83.5万円が手元に来ます。
しかしiDeCoで運用すれば運用益は非課税であるため、104万7,467円が丸々手元に来ます。
ここはつみたてNISAと同様のメリットですね。
iDeCoのメリット③:受け取り時に税制優遇がある
最後に、受け取り時にも税制優遇があります。
iDeCoは受け取り方法として、年金として受け取るか一時金として受け取るか選択することができます。(両方を組み合わせて受け取ることもできます)
年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金として受け取る場合は退職所得控除が適用されます。
ざっくりとした説明は以下となります。(楽天証券のiDeCoを参照)
公的年金等の収入の合計額が65歳未満だと70万円まで、65歳以上だと120万円までは税金がかかりません。(超えた場合、計算式によって算出された金額が課税対象となります)
iDeCoの加入年数に応じて退職所得控除の計算式によって算出します。
- 20年以下の場合…40万円×加入年数(80万円以下のときは、80万円)
- 20年超の場合…800万円+70万円×(勤続年数-20年)
税金が関わるため複雑になりますので、受け取り時にはシミュレーションするようにしましょう。
iDeCoのメリット④:差し押さえ禁止財産となる
iDeCoの最後のメリットとして差し押さえ禁止財産となることです。
差し押さえ禁止財産については、以下を引用します。
公正証書や調停などでお金を支払う旨約束したり、判決等による支払い命令が出てもなお、お金を払わない債務者に対しては、債務者の財産を差し押さえ、競売して、強制的に金銭債権を回収することができます。
ただし、債務者にも生活があるため、法は、債務者やその家族が生活していく上で必要不可欠な財産・必要最低限度の財産などについては、差し押さえを禁止、差し押さえできないとしています。
https://saiken-law.com/base/315/
もし事業などが失敗して自己破産したとしても、iDeCo口座は差し押さえられないということですね。(ただし税金の滞納をした場合は別)
自分の資産が固く守られているのは大きなメリットになります。
また、他の差し押さえ禁止財産の一例として以下のものが挙げられます。(リンク先参照)
- 生活に必要な衣類、家具、台所用品、寝具など
- 1ヶ月間の生活に必要な食料及び燃料
- 現金66万円まで
- 職業上必要なもの(職業が農家の場合は農機具、肥料など)
- 給料(ただし4分の1は差し押さえ可能。また33万円を超える部分も差し押さえ可能)
iDeCoのデメリット
反対にiDeCoのデメリットは以下の通りです。
- 原則60歳まで引き出せない
- 各種手数料がかかる
- 税制優遇を最大限に受けるのは難しい
- 掛け金を変更できるのは年1回なので、資金に余裕がないと生活が厳しくなってしまう
それぞれ見ていきましょう。
iDeCoのデメリット①:原則60歳まで引き出せない
iDeCoのデメリットとして一番に挙げられるのが、原則60歳まで引き出せないことでしょう。
目的が老後資金なので簡単に引き出せてしまうのは問題になってしまいますが、それでも60歳まで引き出せないという資金拘束は厳しいですね。
例えば20歳でiDeCoを始めたとしても、30歳、40歳といったときにライフステージの変化によってお金が必要になることもあると思います。
これが特定口座やNISA口座、預金口座の場合は、自分のタイミングで引き出せるので問題ありません。
そういったときでもiDeCo口座から引き出せないというのは大きなデメリットになりますので、iDeCoはよく考えてから始めていきましょう。
iDeCoのデメリット②:各種手数料がかかる
iDeCo口座では特定口座やNISA口座と異なり、口座に対して手数料が発生します。
主に、国民年金基金連合会・事務委託先金融機関・運営管理機関の三者に対して手数料を支払う必要があります。
ただし、このうち運営管理機関は楽天証券・SBI証券といったネット証券の場合は無料となります。
どういった内容に対して手数料が発生するのかについては、以下の表の通りです。
| 内容 | 国民年金基金連合会 | 事務委託先金融機関 | 運営管理機関 | 合計金額 |
| 新規加入時/移換時手数料 | 2,829円(初回のみ) | – | 0円 | 2,829円 |
| 口座管理手数料 | 105円/(掛け金初出時) | 66円/月 | 0円 | 171円 |
| 給付事務手数料等 | – | 440円(振込1回ごと) | – | 440円 |
特定口座やNISA口座では上記のような手数料はかかりませんが、iDeCo口座の場合は手数料がかかることを認識しておきましょう。
iDeCoのデメリット③:税制優遇を最大限に受けるのは難しい
iDeCoでは掛け金拠出時・運用時・受け取り時のすべてにおいて優遇税制を受けることができますが、最大限に恩恵を享受するには難易度が高いです。
まず掛け金拠出時ですが、例えば専業主婦など収入が無い場合は所得控除の恩恵を受けることができないため注意が必要です。
なぜなら収入から控除を引いた金額に対して課税所得がかかるので、収入がそもそも無い場合は課税されないからですね。
この点は注意しましょう。
次に運用時ですが、元本確保型の商品を選択すると非課税メリットを全く活かすことができません。
運用時は運用した利益に対して非課税となりますが、元本確保型の商品の場合は利益が出ないため非課税メリットを活かすことができません。
さらに、デメリット②でも触れましたが各種手数料がかかるため、実質的には損益としてはマイナスになります。
長期間運用していくのであれば、リスク商品に投資していきましょう。
最後に受け取り時ですが、メリット③でも触れましたが、年金として受け取るか一時金として受け取るか選択することができます。
ただし優遇税制を最大限受けようと思うと、考えないといけないことが多く難しいです。
基本的には両方を組み合わせて受け取ることになると思うので、受け取り時のシミュレーションはするようにしましょう。
iDeCoのデメリット④:掛け金を変更できるのは年1回なので、資金に余裕がないと生活が厳しくなってしまう
iDeCoは職業ごとに掛け金の上限が決まっています。(以下の表を参照)
| 職業 | 掛け金の上限(月額) |
| 自営業者 | 6.8万円 |
| 公務員 | 1.2万円 |
| 会社員 | 1.2万円、2万円、2.3万円のいずれか |
| 専業主婦 | 2.3万円 |
上記の上限までで掛け金の最低金額は5,000円で1,000円単位で変更することができますが、年1回しか変更することができません。(変更には加入者掛金額変更届を提出する必要がある)
つまり必ず拠出できるであろう余剰資金でiDeCoを始めないと、今の生活が厳しくなってしまうので注意が必要です。
なおどうしても資金が捻出できない場合は、加入者資格喪失届を提出することで一時停止することができます。
掛け金の変更・一時停止など届け出をしないといけないため、無理の無いような掛け金を拠出をしていく必要があります。
まとめ:iDeCoの特徴とメリット・デメリットを知り、上手に活用していこう!
本記事では、iDeCoの特徴とメリット・デメリットについて解説してきました。
iDeCoの特徴としては以下の通りです。
- 自分自身で老後資金を作るための制度である
- 国民年金被保険者の20歳~64歳が加入できる
- 掛け金を拠出・商品を選択し運用する
- 職業ごとに掛け金の限度額がある
またiDeCoのメリット・デメリットは以下の通りです。
- 掛け金が全額所得控除になる
- 運用益が非課税になる
- 受け取り時に税制優遇がある
- 差し押さえ禁止財産となる
- 原則60歳まで引き出せない
- 各種手数料がかかる
- 税制優遇を最大限に受けるのは難しい
- 掛け金を変更できるのは年1回なので、資金に余裕がないと生活が厳しくなってしまう
最後に、個人的にiDeCoをおすすめできる人について紹介します。
- 60歳になるまで15年以上運用できる人
- 60歳まで使わなくても良い余剰資金がある人
- 安定した収入が見込める人
これらの意見を踏まえて、iDeCoを始めてみたいと思った方は証券口座を開設し、別途iDeCo口座も開設する必要があります。
iDeCoに限定せず、投資する際はおすすめの証券口座となっていますので、ぜひ検討してみてください。(iDeCoは1人1口座)
また、iDeCoのおすすめファンドについても記事にしていますので、こちらも参考にしてみてください。
関連記事です。
iDeCoはハードルが高いなと感じた人向けに、つみたてNISAもおすすめできる制度なので、ぜひ参考にしてみてください。
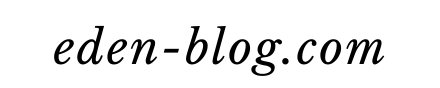
とは?】メリット・デメリットを解説!.png)


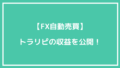

コメント