本ブログでは米国を中心としたインデックス投資をおすすめしています。
日本株と比較しても米国株の方がメリットが多いですからね!
特に投資初心者の方に対しては、つみたてNISAで投資信託に投資することをおすすめしています。
しかし米国株には、つみたてNISAで投資できないような魅力的な株やETFも多いです。
そこで本記事では、さらに一歩踏み出して直接アメリカの株式に投資してみたいといった方に
- 米国株投資の魅力
- SBI証券で米国株投資をするメリット
- SBI証券で米国株投資をするデメリット
を紹介していきます。
もし
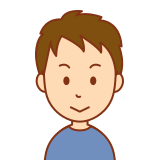
初心者だけど、これから投資を始めてみたい!
という方がいましたら、まずは投資信託から始めてみるのがおすすめです。
こちらの記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
米国株投資の魅力
米国株投資の一番の魅力は、多様な商品をもつ米国市場にアクセスできることにあります。
米国市場のため米ドルで購入することになり、日本では購入できない株に対して投資することができます。
例えば
- Google(グーグル)
- Apple(アップル)
- Facebook(フェイスブック)※Metaに社名変更しました
- Amazon(アマゾン)
といった新進気鋭のGAFAであったり、
- Coca-Cola(コカ・コーラ)
- McDonald’s(マクドナルド)
- P&G(プロクター・アンド・ギャンブル)
といった昔から馴染みのある企業に投資することができます。
また、魅力的なETF(上場投資信託)も多数あります。
有名なところでは
- VT(全世界の投資可能な時価総額98%以上の株式を詰め合わせたファンド)
- VTI(米国の投資可能なほぼ100%の株式を詰め合わせたファンド)
- VOO(米国の主要指数であるS&P500に連動するファンド)
があります。
ちなみに、VT・VTI・VOOといったETFは投資信託を通して購入することもできます。
それぞれ
- SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
が対応しています。
上記のように、米国ETFの中でも日本の投資信託を通して購入できるようになっていますが、まだまだ少ないのが現状です。
例えば
- SPYD(S&P500のうち、配当利回りが高い上位80銘柄に均等割合で投資するファンド)
- VGT(米国の情報技術セクターに投資するファンド)
- VHT(米国のヘルスケアセクターに投資するファンド)
のようなETFがありますが、これらは日本の投資信託を通して購入することはできません。
その他、世界の中心であるアメリカには世界中の企業が米国市場に上場しています。
日本でいうと
- トヨタ自動車
- ソニー
といった企業も米国市場に上場しています。
このように世界中の企業が集まり、なおかつ多様な商品にアクセスできることが米国市場の魅力になります。
米国株投資はSBI証券がおすすめ
まず、国内の主要ネット証券3社(SBI証券、楽天証券、マネックス証券)の米国株投資の環境はほとんど同じです。
3社とも2019年7月には米国株の最低取引手数料を5ドルから0ドルへ引き下げています。
また、2020年1月には米国ETF(9銘柄)の買付手数料無料化するなど、競争も活発に行われています。
以下がその際に買付手数料が無料となった米国ETFです。
| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
| VT | VT | VT |
| VOO | VOO | VOO |
| VTI | VTI | VTI |
| SPY | SPY | SPY |
| IVV | RWR | IVV |
| EPI | GLDM | EPI |
| DHS | AIQ | DHS |
| DLN | FINX | DLN |
| DGRW | GNOM | DGRW |
後述しますが、SBI証券はさらに2022年4月から買付手数料無料のETFを入れ替えており、基本的にメリットになっています。
その中でもSBI証券で米国株投資をするメリット・デメリットについて書いていこうと思います。
SBI証券で米国株投資するメリット
SBI証券で米国株投資するメリットとして
- 住信SBIネット銀行を活用することで為替コスト(手数料)が安い
- 米国株式・ETF定期買付サービスでの積立投資
- 主要ネット証券で取り扱い銘柄数が最多
- 幅広い範囲の米国ETFが買付手数料が無料となっている
があります。
それぞれ紹介していきます。
SBI証券で米国株投資するメリット①:住信SBIネット銀行を活用することで為替コスト(手数料)が安い
米国株を買付けする場合、円貨決済と外貨決済の2種類存在しています。
それぞれの特徴を簡単に説明すると以下の通りです。
- 円貨決済…自分が持っている円からドルへ自動的に交換し米国株を購入
- 外貨決済…自分が持っているドルでそのまま米国株を購入
円貨決済の方が楽ですが、円からドルへ交換する (ドル転) 際に為替コストがかかっており、1ドルあたり25銭となっています。(SBI証券・楽天証券・マネックス証券とも同じ)
このコストを減らすために外貨決済にしたいですが、ドル転はどこかで行わなければなりません。
その際に登場するのが住信SBIネット銀行となります。
住信SBIネット銀行を利用すると
- 外貨預金の場合、1ドルあたり6銭(円貨決済の4分の1以下)
- 外貨積立の場合、1ドルあたり3銭(円貨決済の8分の1以下)
という低コストでドル転することができます。
また住信SBIネット銀行は外貨預金セールというキャンペーンをやっているときがあります。
もしそのキャンペーン時にドル転すると、為替コストがなんと0銭になるため狙ってみるのもありだと思います。
ここまでを表にまとめると以下のようになります。
| ドル転方法 | 為替コスト(1ドルあたり) | 1ドル100円で100万円分ドル転した際の手数料 |
| 円貨決済 | 25銭 | 2500円 |
| 外貨預金 | 6銭 | 600円 |
| 外貨積立 | 3銭 | 300円 |
| 外貨預金セール | 0銭 | 0円 |
あとは住信SBIネット銀行からSBI証券へドルを出金させてることで、外貨決済で米国株を購入することができます。(同じSBIグループなので連携はバッチリです!)
円貨決済より手間が増えてしまいますが、為替コストを抑えることができますのでぜひ利用するのをおすすめします。
SBI証券で米国株投資するメリット②:米国株式・ETF定期買付サービスでの積立投資
米国株式・ETF定期買付サービスは、投資信託では当たり前となっている積立投資が米国株でもできるサービスとなっています。
SBI証券では2018年3月から「米国株式・ETF定期買付サービス」を開始しています。
今まで他社でもやっていませんでしたが、2021年12月にようやく楽天証券も米株積立というサービスが開始しました。
SBI証券の「米国株式・ETF定期買付サービス」と、楽天証券の「米株積立」を比較してSBI証券の方が優れている点として以下の2点があります。
- SBI証券では毎月・毎週だけでなく毎日積立も可能(楽天証券では毎月・毎週のみ)
- SBI証券では積立の最低設定金額が1円から可能(楽天証券では1万円から可能)
すごい大きなメリットというわけではありませんが、細かいところまで手が届いているSBI証券の方が使いやすいと思います。
SBI証券で米国株投資するメリット③:主要ネット証券で取り扱い銘柄数が最多
主要ネット証券3社の米国株の取り扱い銘柄数は以下のようになっています。
| 証券会社 | 取り扱い銘柄数(2020/3/8調査) | 取り扱い銘柄数(2021/5/2調査) | 取り扱い銘柄数(2022/3/24調査) |
| SBI証券 | 3305 | 3975 | 5135 |
| 楽天証券 | 2965 | 3726 | 4760 |
| マネックス証券 | 3591 | 4099 | 4912 |
今まではマネックス証券が最多の取り扱い銘柄数を誇っていましたが、2022年になってSBI証券が最多数となりました。
SBI証券では2022年を「米国株式サービス強化元年」と位置づけており、取り扱い銘柄数が最多になったことからもわかるように相当力を入れています。
SBI証券で米国株投資するメリット④:幅広い範囲の米国ETFが買付手数料が無料となっている
SBI証券では、2020年1月から米国ETF9本の買付手数料を無料としていましたが、2022年4月から銘柄の入れ替えが行われ、以下の米国ETF10本が買付手数料無料となります。
- VT
- VTI
- VOO
- EPI
- GLDM
- QQQ
- SPYD
- AGG
- VGT
- IYR
今まではVOO、IVV、SPYとS&P500ETFが重複していましたが、今回の改定でVOOに一本化したことですっきりしました。
また、ネットでも人気となっているETFのQQQ、SPYD、AGGの買付手数料が無料となっているのがうれしいですね!
SBI証券で米国株投資するデメリット
続いて、SBI証券で米国株投資するデメリットです。
米国株の投資環境は、主要ネット証券3社ほとんど変わらないですが、強いて言えば以下の点かなと思います。
- 時間外取引ができない
- 注文の種類が多くない
それぞれ見ていきます。
SBI証券で米国株投資するデメリット①:時間外取引ができない
通常、米国市場は日本時間で
- 【夏時間】22:30~5:00
- 【冬時間】23:30~6:00
で取引されていますが、時間外取引はこの時間以外にも取引することができます。
具体的には日本時間の
- 【夏時間】21:00~22:30(プレ・マーケット)、5:00~9:00(アフター・マーケット)
- 【冬時間】22:00~23:30(プレ・マーケット)、6:00~10:00(アフター・マーケット)
に取引することができます。
SBI証券では時間外取引をすることができませんが、マネックス証券では時間外取引ができますのでSBI証券のデメリットとなります。
SBI証券で米国株投資するメリット②:注文の種類が多くない
SBI証券では注文の種類として
- 指値注文
- 成行注文
- 逆指値注文
が用意されていますが、マネックス証券では上記3つにプラスして
- トレールストップ注文
- OCO注文
- 連続注文
を行うことができます。
注文の種類が多いということは、それだけ色々な戦略を立てることができますが、長期的にドルコスト平均法で積み立てていく場合には必要ないかなと思います。
まとめ:米国株投資の魅力を理解して、SBI証券で投資を始めよう!
本記事では、米国株投資の魅力とSBI証券で米国株投資をするメリット・デメリットを解説しました。
米国株投資の一番の魅力は、多様な商品をもつ米国市場にアクセスできることです。
またSBI証券で米国株投資をするメリット・デメリットは以下の通りです。
- 住信SBIネット銀行を活用することで為替コスト(手数料)が安い
- 米国株式・ETF定期買付サービスでの積立投資
- 主要ネット証券で取り扱い銘柄数が最多
- 幅広い範囲の米国ETFが買付手数料が無料となっている
- 時間外取引ができない
- 注文の種類が多くない
SBI証券で米国株を始めることによるデメリットもお伝えしましたが、個人的にはメリットの方が大きいと思いました。
SBI証券の場合は「為替コストの安さ」、「米国株式・ETF定期買付サービス」のようなサービスから見てみると、頻繁に売買せず長期的に積み立てていく長期投資に向いています。
逆に米国株に短期投資したい場合は少し見劣りするかなという感じです。(ただし全くおすすめできないわけではありません)
米国市場は現在に至るまで長期的に右肩上がりの市場ですので、ぜひSBI証券で米国株投資を始めてみてはいかがでしょうか?
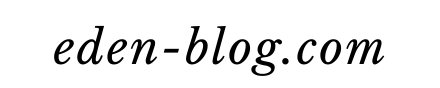



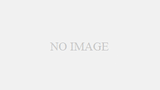
コメント