不労所得って誰もが憧れるし響きが良いですよね(笑)
本ブログでは投資初心者対してインデックス投資をおすすめしていますが、インデックス投資だけではキャッシュフローは増えていかないため、日々の生活は良くなりません。
そこでお伝えしたいのが高配当株投資になります。
高配当株投資とは、名前の通り高配当となっている株を購入して高い配当金を得る方法です。
高配当株投資では具体的には年間3%(税引き後)以上を狙うことが多いです。(100万円投資したら年間3万円の配当金になります)
そんな高配当株投資のメリット・デメリットを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
高配当株投資のメリット
高配当株投資のメリット①:完全な不労所得である
高配当株投資のメリットとして一番に挙げたいのが、完全な不労所得であるということです。
不動産投資も不労所得として代表されることもありますが、管理会社のやりとりであったり入居者との交渉であったり、事業所得の一面があります。(私自身不動産投資はしていないので憶測も含まれていますが)
その点高配当株投資であれば、一度購入してしまえばチャリンチャリンと配当金が定期的に振り込まれてくるので、何もすることがなくなります。
個別企業の株を購入している場合は定期的にメンテナンス(業績不振なので売ったり、逆に買い増ししたり)する必要がありますが、人気の米国高配当ETFのような商品を購入すれば、メンテナンスすらもETF側で自動的にやってくれるため、より不労所得感が強くなります。
高配当株投資のメリット②:収入の分散が可能
世の中の数多くの方が収入源が一つしかないと思います。
サラリーマンであれば給与所得ですね。
私はこれからの時代においては、収入源が一つだけだと危険だと感じています。
- 病気や怪我によって仕事が続けられなくなる
- AIの発達や日本の国際競争力の低下によって仕事自体が無くなる
- 少子高齢化による税金負担が増加
人生100年時代と言われるようになっているため、労働期間の長期化に伴って上記のようなことが自分の身に降りかかる可能性もあります。
またそうした中でも副業が注目され始めていますが、副業は難易度が高く芽が出るまでに時間がかかることもあります。
そこでおすすめしたいのが、株式投資をして配当金を貰うということです。
今はネットでの取引が盛んになっていることもあり、手軽に少額から投資を始めることができます。
おすすめの証券会社は
- 日本株であればSBIネオモバイル証券
- 米国株であればSBI証券
になります。
それぞれの記事もありますのでぜひ参考にしてみてください。
高配当株投資のメリット③:貰える配当金が計算しやすい
配当金を目的とする投資のメリットとして、貰える配当金が計算しやすいというものがあります。
Yahoo!ファイナンスなどで銘柄を探すと参考指標があり、その中に「1株配当」という項目があります。

上記はNTTの参考指標ですが「1株配当」が110円となっており、これを参考に貰える配当金を計算することができます。
「1株配当」は配当を出している会社自身が予想している配当金のため、余程のことがない限り変更はありません。
未来の株価は誰にも読めないですが、配当金の水準はある程度読めるため計算しやすく投資計画が立てやすいことがメリットになります。
高配当株投資のメリット④:増配によって貰える配当金が増えていく
高配当株に限りませんが、企業の業績が好調だと配当金を増やすことがあり増配と呼びます。
例えばKDDIの配当金の推移は以下のようになっており、毎年増配していることがわかります。

増配を毎年繰り返すことを連続増配と呼びます。
KDDIは2022年3月も増配することを発表しており、これが実現すると20年連続増配となります。
ちなみに日本国内の最高は花王の31年連続増配になります。(2021年12月で32年連続増配になる見通し)
さらにアメリカに目を向けると、60年以上連続増配している銘柄もあります。
日本だと株主還元意識がアメリカよりも弱いため、今後も増配してくれる企業を選ぶのは難しいですが、少なくとも減配してしまうような銘柄を避けるように丁寧に選んでいきたいですね!
高配当株投資のデメリット
高配当株投資のデメリット①:購入タイミングが難しい
高配当株投資のデメリットとして、購入タイミングが難しい点が挙げられます。
基本的に株価が下がっているタイミングで、ある程度まとまった額で購入することになるため逆張り投資になります。
問題は株価がどこまで下がるのかわからない点です。
コロナショック時は、一気に下がって一気に回復したため購入タイミングが一瞬でした。
しかしリーマンショック時は、数年に渡り低迷していたため早いタイミングで購入してしまうと、その後ズルズルと下がっていくのを眺めることしかできなくなってしまいます。
どの状況にでも対応できるようにリスク許容度の把握や資金管理が重要になってきます。
その点インデックス投資ではタイミングを測る必要はなく、ドルコスト平均法で淡々と積み立てていけば良いので楽ですね。
一応高配当株の購入の目安についても記事にしていますので、ぜひ参考にしてみてください。
高配当株投資のデメリット②:資産の最大化には向かない
高配当株投資は資産の最大化に向いていないこともデメリットになります。
なぜかというと高配当株投資は資産拡大を重視しておらず、キャッシュフローの水準を意識しているためです。
配当金を目的とする投資の場合、配当金が支払われ手元に来るたびに税金がかかってしまうため、再投資しようとしても税金分複利の力が弱くなってしまいます。
逆に投資信託で行うインデックス投資の場合、配当金は投資信託内で自動で再投資してくれます。
その際、税金はかからないため複利の力を最大限活かしながら投資することができます。
インデックス投資を選択するのか高配当株投資を選択するのか、投資に何を求めるのかを考えていきたいですね。
高配当株投資のデメリット③:減配によって貰える配当金が減ってしまう
高配当株のメリットで増配を挙げましたが、逆に企業の業績が悪化すると配当金を減らしてしまうことがあり、このことを減配と呼びます。
例えばJT(日本たばこ産業)の配当金の推移は以下のようになっています。

JTは1994年に上場してから一度も減配したことがありませんでしたが、2021年12月で一株配当が130円と減配してしまいました。
JTの減配は当時大きなニュースとなりました。
リーマンショック時に減配していなくても、コロナショック時に減配してしまうこともあるという教訓ですね。
さらに業績が悪化すると配当金を全く出さない無配になることもあります。
無配になりそうな銘柄を避けることはある程度できそうですが、JTのように盤石と思われる企業でも減配してしまうので銘柄選びは難しいですね。
そのため、いろいろな業界(セクター)に分散させながら、出来るだけ減配しにくい銘柄を選ぶ必要があります。
まとめ:高配当株のメリット・デメリットを把握して不労所得を得よう!
本記事では高配当株投資のメリット・デメリットを解説してきましたので、それぞれ復習していきましょう。
- 完全な不労所得である
- 収入の分散が可能
- 貰える配当金が計算しやすい
- 増配によって貰える配当金が増えていく
- 購入タイミングが難しい
- 資産の最大化には向かない
- 減配によって貰える配当金が減ってしまう
上記のような高配当株投資のメリット・デメリットを踏まえて、投資を始めてみてはいかがでしょうか?
本文中でもおすすめしましたが
- 日本株の場合、SBIネオモバイル証券
- 米国株の場合、SBI証券
がおすすめの証券会社となります。
それぞれに関する記事もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
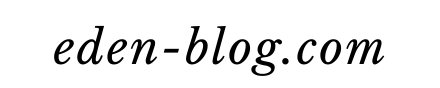




コメント